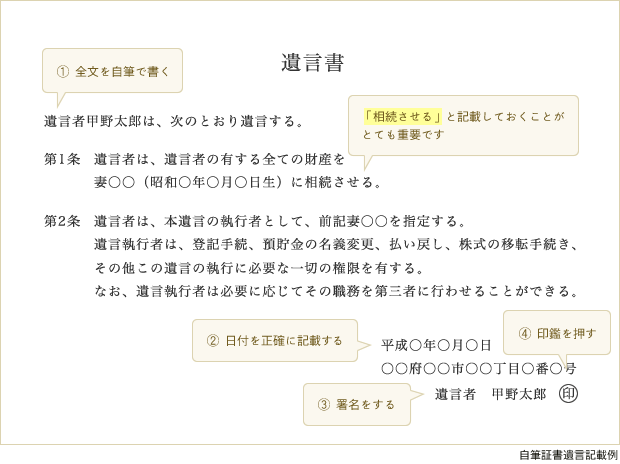相続は、人の死亡によって開始します。相続には「法定相続」と「遺言による相続」があります。「法定相続」とは民法で定められた相続人や相続分で相続することを言い、「遺言による相続」とは遺言書に記載された内容で相続することを言います。「法定相続」と異なる内容の遺言書がある場合、遺言の内容が優先されることになります。
相続登記
被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合は、お忘れにならないうちに相続登記をすることをお勧めします。時間の経過とともに相続関係が複雑になることが予想されるからです。ちなみに相続税の申告期間は10ヶ月以内とされています。相続登記をするためには相続財産や相続人を特定する必要があります。相続人を特定するためには被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を取得する必要があり、その後、遺産分割協議書を作成するなど専門的知識が必要となります。
- 相続登記に必要な書類
- (1)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票【本籍記載のあるもの】
- (2)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(出生~死亡まで)
- (3)相続人の戸籍抄本又は謄本
- (4)相続人の住民票【本籍記載のあるもの】
- (5)相続する不動産の固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書
- (6)遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書
- (7)登記済権利証(物件情報等確認のため)
相続登記の流れ

法定相続分
配偶者は常に相続人となります。
| 第1順位 | 直系卑属(子)(配偶者2分の1 子2分の1) |
|---|---|
| 第2順位 | 直系尊属(親)(配偶者3分の2 親3分の1) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1) |
後順位の人は先順位者がいない場合にのみ相続人となる。
遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。協議がまとまらないときは家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。遺産分割前はすべての相続財産を相続人で共有している状態です。遺産分割をすることにより長男は甲土地、次男は乙土地を取得すると決めることができます。また、長男が甲土地・乙土地を取得する代わりに次男に金銭を与えるといった内容の協議をすることも可能です。
自筆証書遺言
遺言としてよく利用されるもので、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印(実印)することでできます。自身で作れるので費用はかかりませんが、せっかくの遺言が要式不備により無効になったり、遺言内容が曖昧な場合は相続人を困らせてしまう危険性があります。